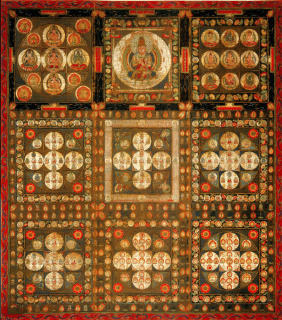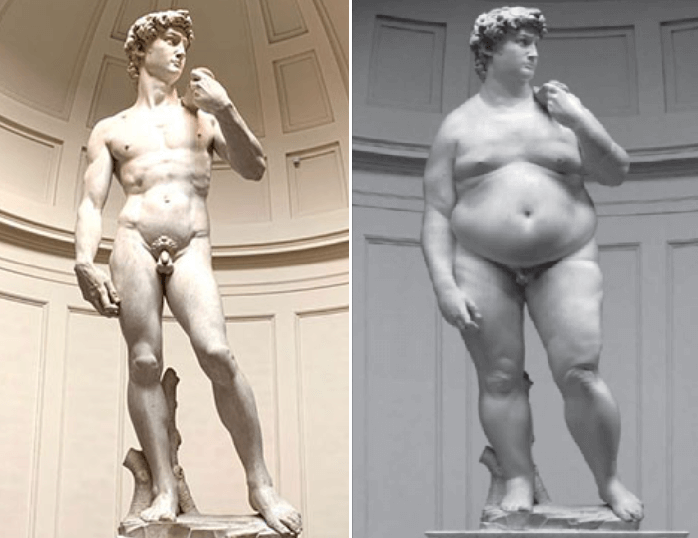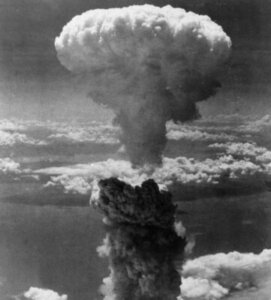サイト訪問統計分析レポート(2022年11月)
量子理論解釈への関心拡大
この11月は、一日平均訪問者数(赤線)は165人で、10月からは20人との増加となり、ふたたび順調な増加傾向にもどりました。
10、11月と連続した海外滞在により、新たな記事の掲載がなかったにも拘わらず、11月は顕著な増加となりました。そのけん引役は、理論人間生命学の第1部と第5部で、ことに後者は「量子的人間観」と題され、この最先端の物理理論の私たちの生活に結び付けた解釈をテーマとしており、理論人間生命学のハイライトとも言える部分です。それが増加しているのは、なかなか興味深い読者反応です。 続きを読む