ここに「補完章」と題するのは、副次的なものを補うという意味ではなく、既述の議論に、学的体系を根本的に異にする新たな視角を加えるという主旨です。すなわち、これまでの9章は、西洋由来の科学を土台に、その方法的規範である〈要素還元主義〉が切り拓いてきた系譜をたどってきたものです。そして、その最終的な到達点が、その要素還元的手法の行き着いた先端に見出される、科学がまさに非科学的な視点を必要としているとも表現されるその冥界でした。そこに、要素還元に拠らないオルターナティブな学的体系として、遠く古代よりの経験的手法を特徴とする東洋の学的体系に焦点が当てられようとしている壮大な変貌を目撃してきたのでした。
東洋思想という〈経験科学〉
そうした発想転換を述べるにあたって、まず表明しておかねばならないことは、ここに東洋思想を取り上げるとしても、私はもちろんその広大な領域を述べるにふさわしい者ではなく、せめて言えるのは、日本という東洋の一隅に生まれ育ち、その伝統を無意識も含め少なからず身に着けてきた者に過ぎないことです。その意味では一般的日本人とことに違うところはありません。そうではありますが、中年にいたってオーストラリアに留学した体験をもとに、西洋の一部をなすその異質な環境に身を置いたことから、逆照射的に、東洋的ことに日本的と受け止められる諸要素を身をもって感じてきたことはあえて申し添えたいところです。そして、そうした体験のもとに、ことに、留学体験を生かした仕事からリタイアした生活に入って以後の「人生二周目」において、独自に見出す疑問への取り組みとして、本考察を含む一連の作業に取り組んできています。そうした私的経験を下地に述べられる本稿は、その限りでアマチュア作業ではあり、研究成果とはいっても、変則的なものに違いないでしょう。
このように、東洋思想の分野に独自な着目があるわけですが、そこにさらにいっそう私的な体験として、その東洋思想へのもっとも具体的な発端として健康問題を通じた東洋医学の分野へのやむない関わりがありました。こうして、学的にも私的にも、〈経験〉と言う方法が、期せずして両世界に共通した有効性を持つことに気付かされました。ことに、その経験という、要素還元式ではない個々の具体例を積み上げてゆくという手法は、そうであるがゆえに、科学に代表される西洋的方式とは対照的な、学的新地平を開くものと期待されます。
そうした学的体系のうち、誰にとってもまずは切実な医学の分野において、西洋医学の方法は、科学の一分野としてやはり要素還元主義の方法論に立つものです。それが東洋医学については、人間が人間を相手とした経験のぼう大な積み重ねを集大成してきた集合知によるものです。そうであるからこそ、その発端は三千年をも遡る古い知識に発していて、いかにも、古式蒼然とした知識との様相――一種の誤解や軽視の種――を誇っています。
いうなれば、〈東洋科学〉――この用語は一般には存在しない私の造語――が、西洋由来科学と異なるその根源は、それが〈経験科学〉であるからと特徴付けてもよいでしょう。ゆえにその知識体系は、たとえ集大成されたものであったとしても、関係するそれぞれの人々のもとに個的に蓄積され、それがゆえに属人的な様相を越えられません。そしてその教えも、対人的に伝えられるものが本筋であり、いわば、その「先生」の数だけの違った「流派」が存在することともなり、その世界全体を一望するのは極めて困難であるとも言えます。
ただその一方で、私にとっての個的取り組みという域では、この〈経験科学〉という特性は、自分自身が経てきた私的経緯に一種の同列な重みを与えてくれています。つまりそれは、そうした私独自の見解の有用性の根拠として用いてきた「自分実験」と呼ぶ方法とも重なっており、そうした個的実験から体験的に得る知識とは、フラクタルな規模の差こそあれ、この東洋的な学と方法と、同等なものに拠っていると踏んでいます。
東洋伝統医学の西洋進出
そのような東洋医学の分野で、今日もっとも際立って、それこそ多くの人々――ことに西洋医学によって疎外されてきた患者たち――によって体験的に有効と認められてきているのが、東洋医学の伝統をユニークに今日に伝える、日本伝統医学です。
そこでですが、私にとってこうした日本伝統医学は、正直なところ、「まがい物」とは言い過ぎとしても、時代遅れな印象が否定できないものであったことは確かです。これは日本の近代の歴史的経緯の一産物がゆえと言えますが、他方、その経験本意で治療効果重視の〈体系をなさない累積構造〉は、その従事者にとっても、後述のように、混迷のもとであったようです。
東洋伝統医学のそうした課題を背負いつつ、しかも西洋の地に足を下ろして地道に有効性の定着を開拓しているという事実を伝える、私が注目している今日的文献があります。それが、カナダを拠点に発行されている『North American Journal of Oriental Medicine(北米東洋医学誌)』〔以下「NAJOM誌」〕です。
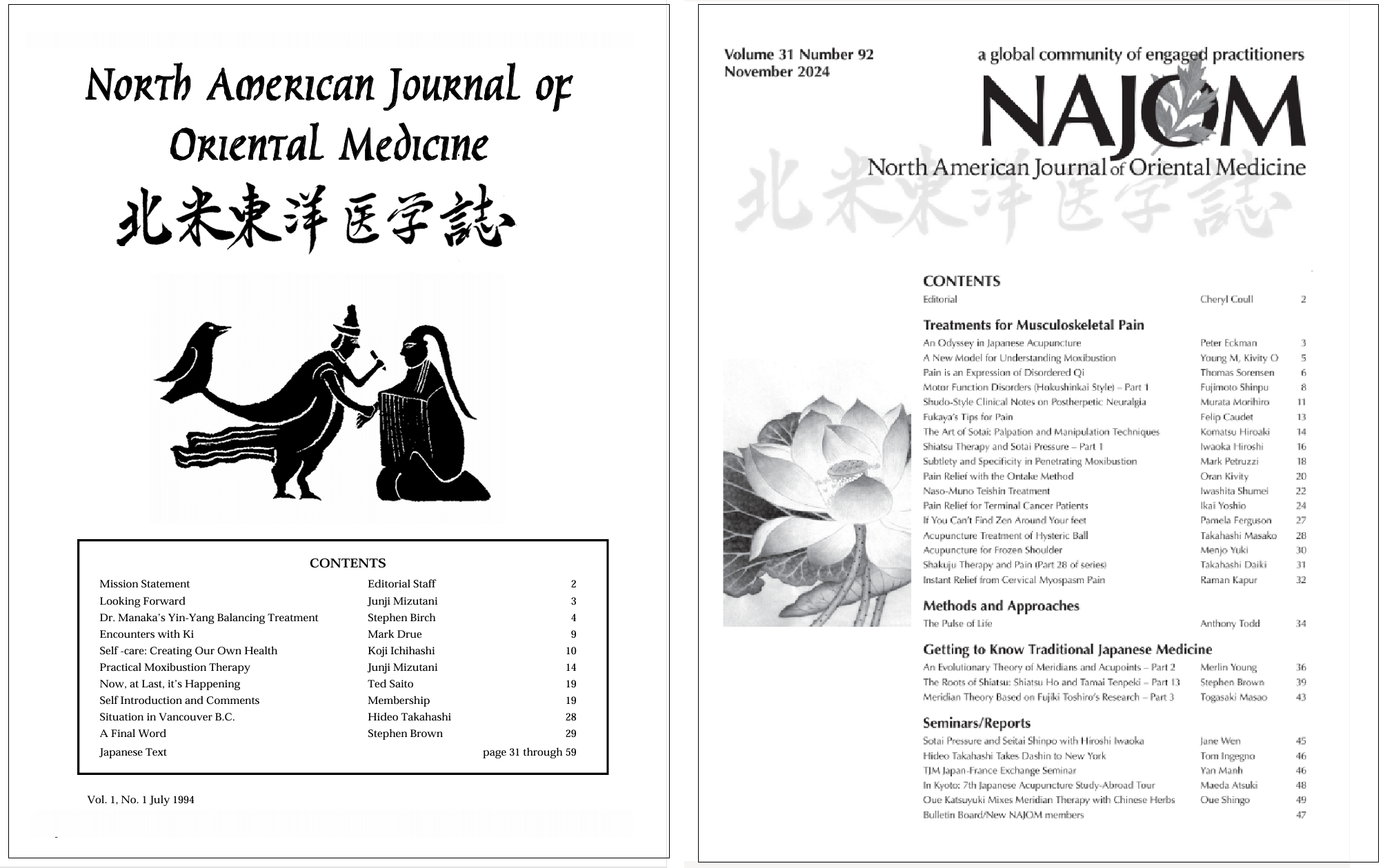
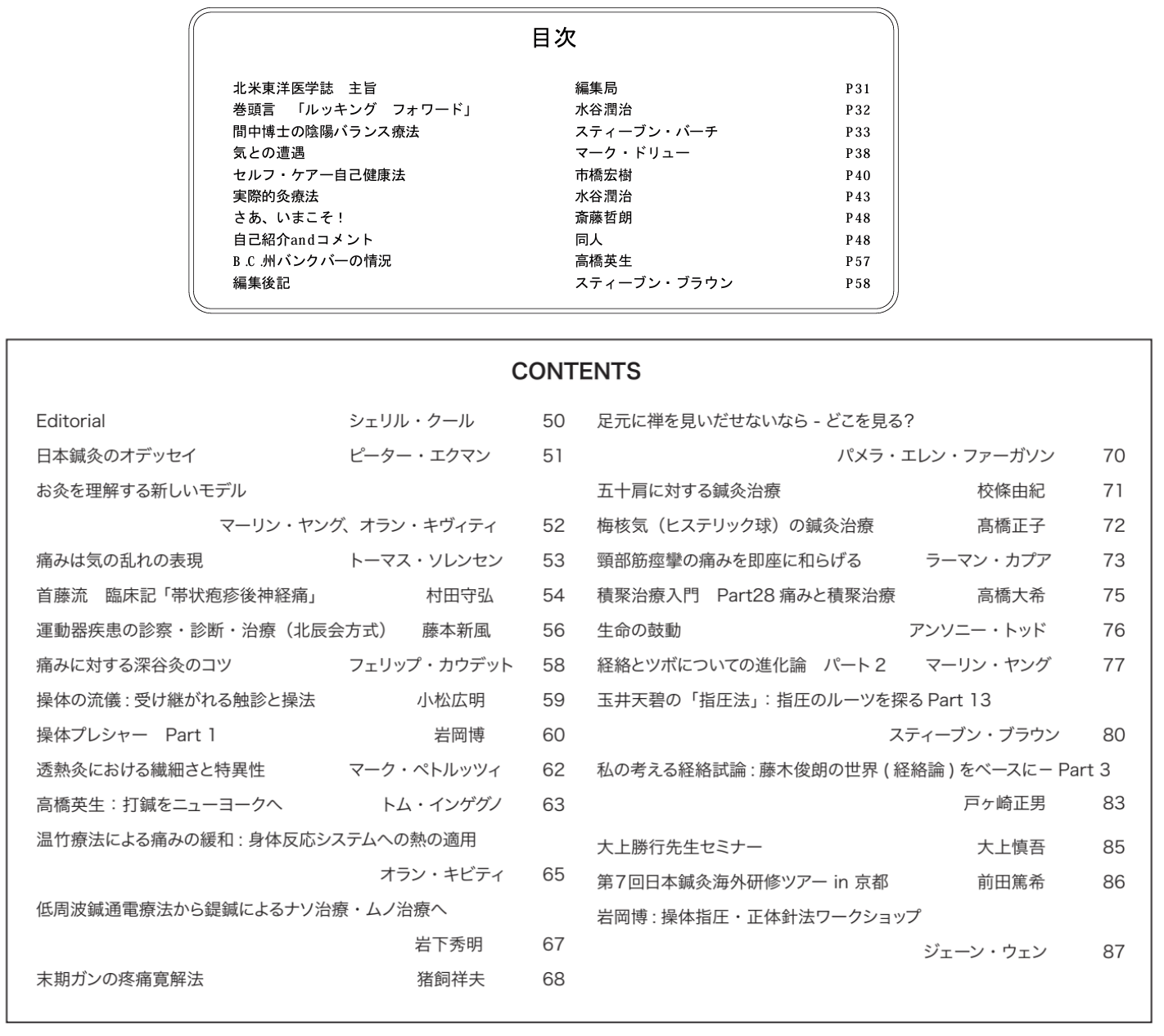
ところで、私がこの文献を取り上げるには、ある特異ないきさつがありました。それは、上記のような体験から東洋思想にアプローチしたいとは願いつつ、私は言葉上、日本語以外の東洋の言語を解せません。そこにこのNAJOM誌が、日本語と英語のバイリンガルな文献として発行され、その壁に穴をあけてくれていました。
もちろん、今日、日本語が東洋の知識体系を表現するにあたり有力な位置を築いているとは言えるでしょう。それは、日本が東洋の片隅にありながら、西洋の知識を先取して吸収してきたという近代の歴史的経緯――日本が持つ両属的文化性――が寄与しています。おそらく、他のアジアの言語でも、こうした東洋的知識をまとめているものはあるでしょうが、私個人としては、残念ながら、それへの直接のアプローチは不可能でした。
「健康的な社会の礎」という普遍的使命
NAJOM誌はその副タイトルに「a global community of engaged practitioners」と示されているように、その分野の実践者の国際的交流誌です。すなわち、通常の学会誌なら「a global journal」とされるところでしょうが、それを「a global community」とされているところに同誌や東洋医学の特徴が見られます。したがって、そのほとんどの記事は実際の治療ケースの記録で、その内容は専門用語で満たされていて、私のような門外漢にとっては、まったくの「猫に小判」です。ただ、まれに掲載されている、決して一般向けではないものの、その理論面や歴史的経緯を扱った記事は、私にとって、その専門世界に入ってゆく貴重な手掛かりとなっています。
1994年、NAJOM誌は創刊され、その実行者の一人であり、以来30年にわたりその編集主幹を務めてきている水谷潤治氏は、創刊号の巻頭言で以下のように述べています。
地陰と天陽に加えて、ここに40名の北米人が会して、天人地の三才となった。/『北米東洋医学誌』と言っても、私たちのなかには、東洋も西洋も、北も南もない。あるのは、陰陽のバランスのとれた、健康な身体を作り上げ、健康的な社会の礎を作りあげるために、この機関誌があるという事実です。/
東洋医療に従事する人々が、広く学術交流し、そして、自分を啓発し磨き上げて行くためのスプリングボードに、この雑誌が成長するように念じるとともに、同人の諸兄に、一層のサポートと寄稿をお願いします。
ここにいみじくも著わされている、学術専門誌というより、文学者の同人誌と見まがいそうな設立趣旨にこそ、東洋医学の個々の体験中心の方法論が語られています。つまり、「健康的な社会の礎」を築くという使命のため、個々の施術者の体験を相互に著し、尊重し、それを学び合って「自分を啓発し磨き上げて行く」という、相手も自分も〈人間主体〉の方法です。
今日、技術進歩は著しくかつ急速で、あたかも、技術進歩こそが人間社会の本髄であり、人間の存在がそれに追随させられているかの様相があります。そしてそこでは、医学という人間が健康であるための学術さえ、技術や専門性が先に立って分割され、むしろ、人間総体のなす意味や価値が背後に押しやられていっている〈既存体制主体〉の傾向が見られます。
それが組織的に推進されている学的あるいは技術的進歩が、これまで人間が手作業でなしてきたルーチン労働から人間を解放すればするほど、むしろ、人間による人間のための働きが前面に立つことが求められてくることです。したがって、専門性や技術が主役である時代であればあるほど、それが何のためかをめぐって、人間の経験に依拠しそれを蓄積してきた東洋的な方法は、その本来の意味をあらためて担うものとして、ますます着目されてゆくものと考えられます。
「経絡」論
東洋伝統医学において、その特色を代表しその方法の中心をも成す考えに、「経絡(けいらく)」と呼ばれる概念があります。これは、身体の持つ働きの相互の経路関係をそう呼ぶもので、西洋医学がその基礎とする解剖学にもとづく物的身体構造の体系とは明瞭な対比を成すものです。
経絡は、東洋医を訪れた際には必ず目にするその身体図に、全身をおおう系統のように描かれてい線状の関係で、あたかも西洋医の言う神経系統や血管体系のごときものです。しかし経絡は、解剖学的な実体をいうものではなく、あえていえば、各部位がそのように結び合っているという機能の関係として示されているものです。その経絡は、上に挙げた最新号の記事「私の考える経絡試論 藤木俊朗の世界(経絡論)をベースに- Part 3」に、こう述べられています。
経絡は解剖学的にはいまだ証明されていないが、機能的には存在しているという説がある。これを多くの人が採用しているが、私もその一人である。
〔戸ヶ崎正男〕
これが、上でも触れた「混迷のもと」で、さらに、そうした経絡の経路を流れるものとして、「氣」(「気」とも書かれる)と呼ばれるものがあります。これは、血液やリンパ液あるいはエネルギーに代わるものと説明はされますが、これまた、解剖学的な実体は確かめられていません。
このように、解剖学的に実体として存在しないものが身体では働いているとの――西洋医学的には根拠を欠く「いかがわしい」――見方は、西洋医学が東洋医学を排除する理由にもなってきたものです。
そこでなのですが、近年、情報生物学と呼ばれる生物学の最先端分野において、体内の微細な科学物質や物理的信号が生命体内の情報伝達媒体として働いているとの発見が続いています。つまりそれは、東洋医学でいう「氣」に相当するものではないかとの見方が、しだいに現実味を帯びたものとなってきてきていると、私見ながら、言えるものです。さらには、バイオインフォマティクスと呼ばれる生命のメカニズムを情報科学によって究明しようとの分野にいたれば、その要素還元の最先端が生命情報とよばれ、いまやAI技術もフル導入されてアルゴリズム化され、この「氣」の分野にすら立ち入ろう――あるいはなり代わろう――としているかの状況が伺えます。
言わば、片やに西洋医学が切り捨ててきた領域があり、他方に古代より東洋医学がくみ上げてきた領域があって、それが経絡というその医学体系の骨格にもなっているとの皮肉な対比です。そして今日、西洋科学の最先端において、情報と解釈される物体でも信号でもあるものが働いているとの新事実が次々に発見されています。つまり、その情報とは実は、西洋医学がこれまで切り捨ててきた――少なくとも未知であった――領域の取り上げであるわけです。
こうして、東洋医学の知見とその実績の中核をなす経絡的で非物質的な領域は、いまや情報という概念を介して医学の東西をまたぐ共通の分野として浮上してきています。ならばそこにおいて、数千年のぼう大で多岐にわたる厚みをほこるその経験的知見の世界は、それこそ、人間対人間の遣り取りの蓄積として創生されてきたもので、そこには、単に情報という還元要素の概念では――ましてやアルゴリズム化されたデジタルな技法では――汲み上げ切れない、人間本来の働きの――あえて言えばアナログな――発揮が潜んでいるはずです。また、そうであるからこそ、その実践者の側には、対人的に伝授さえされてきた治療技法の全人間的な厚みと温和さをも伴ってきたもので、それが来たる新時代のまさに最先端の役割となってゆくものと思われます。いうなれば、その古式蒼然たる技法は、未来の先取りであったとも見直されるべき、まさに「壮大な変貌」です。
新たな「実験」概念
また、近年の科学的手法の中でも、従来は、実験室の内部において、その手法が厳密に管理されたもののみを実験として認めてきた原則に、そうした実験になじまない社会的な現象においても、所定条件の違いがもたらす結果の違いをもって、それを「自然実験」とよんで、一種の実験の結果とみなす考え方も認められてきています。
つまり、東洋的な経験の蓄積も、長い年月を重ねて検証されてきたその厚みは、そういう形の無数の実験の成果とも言えるものであり、その厚みがもつ多様性は、その取り上げ方次第では、貴重なホーリスティックな知的体系を成しうるはずのものです。
たとえば、NAJOM誌の30年にわたる諸記事を見渡すと、欧米生まれで、欧米での高等専門教育を受けた西洋医学の専門家が、そうした西洋基盤の経験を土台に、新たに東洋医学を習得し、両医学世界の融合をはかる試みを続けている研究報告も少なくなく見られます。
もちろん、その逆の例もしかりで、そもそもNAJOM誌発刊の構想も、北アメリカに進出した日本伝統医療の実践者が中心となった試みです。さらに、同誌が日英のバイリンガルな交流の場として発刊され、2024年7月の90号をもって発刊三十年に達しているように、歴史的経緯においては東西の分化はあったものの、それがこうした人間による営為によって、その分化のギャップを克服する橋渡しが積み重ねられてきているわけです。
私は、個人として、自分の生にまつわる様々な課題を考える時、そうした分化の一方に染まっている自分を発見しました。またそれがゆえに、その異世界に興味を抱き、それを学び、また、その地に移って、異なる世界の体験をしてきました。
そうした体験の産物が、たとえばこの10回にわたる記事であり、そもそも、二つの兄弟サイトの運営自体も、そうした経験上の足跡を描いてきたものです。
30周年記念アンケート調査
かくして、門外漢ながらNAJOM誌を購読し、その通読より受ける印象は、率直に申せば、科学としての体系とは比肩できない、一種の輪郭のおぼろげさを発見せざるを得ません。もちろんその理由は、上述のように、東洋医学や日本伝統医学の手法が、経験例の蓄積にあって、そこに明確な分析や物的因果関係の実証を欠くためです。そのため、過去において、経絡思想に関し、物的存在か機能の存在かめぐるいわゆる「経絡論争」が展開され、その肯定、否定論が交わされました。結局、その論争に決着はつかず、そうした一種の水掛け論よりむしろ、治療の実践的成果に焦点を当てた臨床上の実務論として発展してきているようです。そもそも、対象の捉え方の原理的発想が異なっている――要素に還元して見るか、ことを分けないで全体として見るか――のですから、決着が得られないのも当然でしょう。
アマチュアながら私は、近年の様々な学的発展を見聞きするにつけ、既述のように、科学の末端におけるある意味で哲学的な視界抜きでは突破できない、次元を異にする新局面を迎えているあり様に注目しています。その意味では、東洋思想のもつ形而上学的な着想と、そうした最先端の科学的知見とが、たがいに原理的に接近しつつあるかの状況が伺えます。そうした今日的な見地から言えば、上記の「経絡論争」にも、こうした新たな論点を加え、その実証の道が開ける可能性もあるかに伺えます。
そこでですが、NAJOM誌は2024年7月に創刊30周年を迎え、この歴史的機会を記念して、購読者への伝統的日本鍼灸に関するアンケート調査を行っています。そのアンケートは、こうした実践面に焦点を絞った治療技法上の質問を中心としたものとなっています。
この12月初め、そのアンケート結果が、その回答者35名による、選択式質問への回答に加え、文面回答の内容が、日本語と英語の両言語に克明に訳されて公表されました。その内容の真意は、これまた私にとっては「猫に小判」なのですが、統計的集計に終わらず、文面回答の一字一句をそのまま公表することで、西洋式の要素還元的な方法の弊害を克服する、ホーリスティックな取り組みへの材料として提供されています。
たとえば、そうした文面回答の中で、私の目に留まったこんな表現があります。「ツボとは」との質問に答えたものです。
人間の身体は、受胎から始まるエネルギー(気)の波形を基盤とする多次元的な創造物です。身体のあらゆる部位がこの波形に関与し、互いに影響を与え合い、影響を受け合っています。古典的な経穴(ツボ)は、刺激の効果が体系化された場所であり、特に十二臓腑(臓器)や経絡に限らず、生物の機能に影響を与えることが数千年にわたる研究で知られています。〔中略〕身体のあらゆる場所が気の波形に影響を与え、また影響を受けますが、これらの関係性のほとんどは不明です。これらはすべて、気と血に影響を与えます。
ここに言う「エネルギー(気)の波形」とは、伝統にならって抽象的な表現なのですが、これはまさに、近年次々と発見されてきている生命情報と呼ばれるものに相当するのではないかと私は受け止めます。つまり、ここまで、東洋と西洋の間のギャップはいま一歩のところまで狭まってきていると、アマチュアであるからこそ単純かつナイーブに、思わされています。
こうして、個々の症状を患う者もそれを治療する者も、共に人間が抱えるそうした要件について、それが人間がかかわっている人間がゆえの両要件なのであり、だからこそ、まさに人間によってしか解決されない性質のものであると思います。とてもじゃないが、ロボット医師によって治癒される要件ではないでしょう。
ちなみに、この公表された回答集に添えられた編集主幹のメッセージは、こう述べています。
添付されているSurveyのファイルを読んで下さい。長い時間を費やし、ようやくSurveyをまとめました。このようなSurveyはNAJOMでしかなしえないでしょう。それ故に、このSurveyはNAJOMからメンバーに対する特別なギフトです。Surveyをしっかりと読むと、日本鍼灸の多様性が理解でき、この多様性がアメリカのメンバーに完全に根付いていることが分かります。30年以上NAJOMが果たした役割もご理解して頂ければ幸いです。
私はここに、人間による人間を相手とした豊穣な土壌を見出します。すなわち、ここに見られる、使命を共有する人たちがそれぞれの経験を持ち寄る柔軟で門戸開放された相互尊重主義です。一方、その他方には、現代医学のそれぞれの専門分野が屹立し合ったプロフェッショナルの世界がなす権威主義の専制王国が君臨している現状があります。
本稿は、そういう東西のギャップに橋が架けられようとしていると、以上のように見出すものです。
結論に代えて
最後に、この〈「MaHa」の学的最前線〉シリーズの結論に代えて、私の個人的感慨を申し添えたいと思います。それは、過去の二度におよぶ世界大戦の時代から一世紀余りを経てきている今日、またしても人類は、禍々しい争いの泥沼に踏み込んで行こうとしています。たとえここで、再び、いずれかの正しさを力によって強引に証明したとしても、それは、良くて、一世紀前の振り出しへの舞い戻りでしかないでしょう。ちなみに、そうした人間としての認識が、今年のノーベル平和賞が日本被団協に授与されたことの意味でしょう。こうした今日、この最終章が採り上げた、東西の文明がそれぞれに築いてきた人類のなす両極というそれぞれの特異性と達成とは、どちらかの勝敗へと向かうべきものではなく、その相互尊重にもとづいた、それだからこその共存と平和のもたらす豊かさへと向かって行く以外の方向はありえないことを示唆していると思います。それこそが、この宇宙の片隅に孤独に存在する一個の惑星上において、人類が永続してゆける唯一の道なのではないかと確信します。
【追記】私は十年前、前立腺ガンの宣告を受け、以来、専門医による全摘の奨めをなんとか断りながら、定期的なPSA検査、生検、MRIによる経過監視を続けて今にいたっています。また、私とNAJOM誌主幹の水谷氏とは学生時代の先輩後輩関係にありながらしばし親交は途絶えていたのですが、三年前、ふとした機会から連絡が再開し、私のガン治療に、氏による灸施術の遠隔指導が加わることとなりました。以降、お灸は欠かさず続けてきており、そしてこの10月の直近のPSA検査では、じりじりと増加を続けてきた数値に降下が見られています。私のガン治療はまだ途上ですが、こうして、際どい接線ながらも一抹の光明――私にとっては紛れもない「自分実験」上の事実――は見えはじめていると受け止めており、西洋医学と東洋医学を織り交ぜた対応の結果の、決して苦くはない結果を得ています。こうした私的体験は、以上の私の「東西架橋」のアイデアを裏打ちする、貴重な土台となっています。